カンファレンスカンファレンスに行って来た
東京界隈で開催されている商売じゃないIT系カンファレンスの主催者や関係者?によるカンファレンスに参加した。
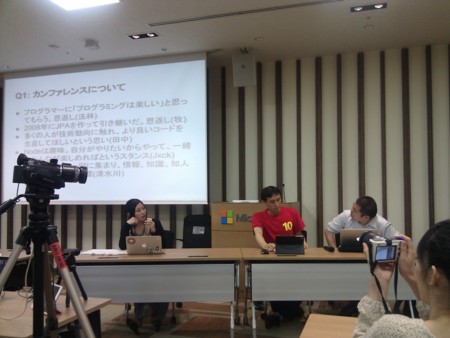
IT系のカンファレンスはそれこそ山のようにあるのだけど、オープンソースの技術系カンファレンスなんかはボランティアによって開催されていたりするのが結構ある。それの主催者とか事務局の人とか参加者とかが集まって、それぞれのノウハウを共有するというような目的で開催されたようだ。http://connpass.com/event/2253/
IT系の勉強会は日々山のように自主的に開催されていて、一体全体どのくらいの数が行われているか見当もつかないけど、数百人規模のカンファレンスも結構な頻度でがしがし元気に開催されている。みんなの大好きなIT勉強会カレンダーを見よ。https://www.google.com/calendar/htmlembed?src=fvijvohm91uifvd9hratehf65k@group.calendar.google.com
今月末にはRubyKaigi 2013が開催されるし、 *1 、ボランティアによる主催ではないがLinuxConなども開催される。 *2
スクリプト系のイベントとしてLLイベント、PHP Conference、YAPC::Asia、PyCon、東京Node学園祭などなどボランティアによって運営されているカンファレンスは少なくない。むしろいっぱいある。

欧米の技術系カンファレンスだとチュートリアルとかトレーニング系のコンテンツなども含めて複数日数、マルチトラックのカンファレンスの参加費は10万円前後になったりするのだが、東京界隈で開催される、上記のようなカンファレンスの参加費はほぼ実費(せいぜい数千円)で極めて廉価になっている。
この低コスト運営は基本的には開催者がボランティアでその仕事に関してはほぼ無給で行っていて、かかった経費に関しても、企業スポンサーなどからの援助でまかなっているからである。
例えばO'reillyが主催するオープンソースのカンファレンスだと、一日パスで$600くらいから$800くらい、5日間のパスだと$1800から$2000を超えたりする(早割があるので購入時期で値段が違う) *3
もちろん規模も違うし、コンテンツも違うので一概に値段だけで比較するのはナンセンスである。
かたやボランティアによる運営、かたやカンファレンスを仕事として仕切る運営。もちろん一長一短があるし単純にどちらが優れているということではない。
RubyKaigiに関して言うと、ボランティアによる運営は運営なんだけど、徐々に欧米型カンファレンスに近づきつつあるような気がする。ただそれでも、参加費が2−3万円というのは欧米型カンファレンスに比べれば圧倒的に安い。
角谷さんによれば、RubyKaigiは人が集まりすぎちゃって、本来来るべき人が来れなくなっちゃったりしたので、(一度仕切り直しをして)、来るべき人だけが来れるようにした、値段を上げて来れないんだったら来なくていいということだ。(わたしの理解では)
わたしはそれはそれで一つの見識だし、その通りだと思う。
ボランティア運営による限界
プロによる仕切りというのは参加者によってはお客さん的に参加できるので楽だ。プログラム委員がコンテンツを決め、それ以外のロジを運営会社へ投げる。カネはかかるがスケールする。問題は参加費用がかかること。
ボランティアによる運営は、コンテンツの作成だけではなく、各種ロジ、会場予約、設定、予算管理、スケジュール管理、講師発表者との連絡、当日の運営、ネットワークの設営、その他なんでもかんでも、ともかく手間暇がかかる。
参加費は安くおさえられる場合がある。
参加者が身内と言うかコミュニティ周りの人がほとんどの場合は、それでもどうにか回る。事務局の驚異的な働きによって見えない部分があったとしても、それを含めてのコミュニティ活動である。
一方で、参加者や発表者がITだけとかある業界内だけで閉じていない場合は、それはまた違った様相を持つような気がする。
「TEDxTokyo アマチュアリズムへの不満」
まったくもって残念なことに、晃太郎はこの企画に関わることで、ここ数日非常に大きなストレスに見舞われました。度重なる運営の不手際と不義理に、怒りのあまりに目がくらむような思いの連続でした。何度も、出演を辞退したい衝動に駆られました。
http://tezumashi.blog42.fc2.com/blog-entry-139.html
個別の事例だけであーだこーだ言うのはフェアではないし、実際はどうだったのか、検証のしようがないので、なんとも言えないことは確かなのだけど、それでも、ロジ周りの細かいところでの気配り段取りに関しては餅は餅屋だと思う。
ボアンティアによるイノベーション
一方でニッチなコンテンツに関しては商用イベントの採算ベースのらないので、そのようなものが商用イベントとして開催されることはない。
東京界隈で多数開催されている勉強会とかカンファレンスは世界的にみればブレークしつつあるんだけど、日本で商用イベントになりにくいエッジのものがぽこぽこ出ているような気がする。
かつてはそれがLinux Users Groupだったし、それがRubyKaigiだったりした。
イノベーションの場として、シリコンバレーやサンフランシスコ界隈と違って、スタートアップの密度が東京ではまだまだ濃くないので、尖ったコンテンツに関してはボランティアによるカンファレンスに依存せざるを得ない。
これってよく考えれば、世界中どこを見渡しても、シリコンバレーほど先端技術の集積している場所はないのだから、東京モデルとあえてここで言うけど、ボランティアによるカンファレンスの開催というのは、地球規模で適用可能なモデルのような気がする。
100人を超える参加者を集めてある技術ネタに関してカンファレンスを開催する。キーノートは海外からその道の第一人者を招聘する。運営はボランティアでプロジェクトチームを形成する。このモデルは世界中どこでも適用可能なんじゃないかな。輸出しましょうよ。みなさま。
商業的に広がってくれば、それはふつーのイベント会社にオマカセすればいいわけでね。
カンファレンスにカンファレンスに出てそんなことを思った。